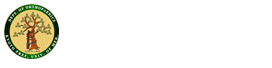病院の紹介
当院は、名神高速道路インターチェンジと国道1号線・8号線の分岐点がある交通の要衝に位置していることから、以前から多くの交通外傷患者が救急搬入されます。またその立地条件から当院周辺には多くの工場が誘致され、その結果労働災害患者も増加し、いつしか「外傷のメッカ」の呼ばれるようになりました。1996年には県下3番目の救命救急センターの指定を受け、2011年には県内で初めて救急科にドクターカーが導入され、さらに2015年4月からは「京滋ドクターヘリ」の運航が開始されて、滋賀県全域のみならず京都山城や福井県嶺南からも重度の外傷患者が搬入されるようになりました。
済生会滋賀県病院公式ホームページ

整形外科の特色

整形外科の救急応需体制としては、救命救急センターに救急担当医を配置し、当直帯は当直医またはオンコール制にて整形外科の24時間対応に努めています。さらに当直帯に臨時手術が入った場合にも、救急受け入れを止めないバックアップ体制を整えて「断らない整形外科」を実践しています。
入院診療では、手術目的の患者や外傷で搬入された患者を中心に常時70余名が入院しています。整形外科の手術件数は、新病院移転当初の2004年は824例でしたが、年々増加して2021年は1720例となりました。
手術の内容は、骨折や腱損傷に対する手術が全体の半数以上を占めていますが、近年QOLの向上を目的とした骨・関節の慢性・変性疾患に対する手術の要望が増えてきました。特に、膝関節手術(TKA、骨切り、関節鏡手術)と、手外科の手術件数は滋賀県最多であり、また当院には脊椎脊髄外科指導医2名が在籍しあらゆる脊椎・脊髄疾患に対応が可能であることから、「済生会滋賀脊椎センター」を設立し、低侵襲脊椎手術に取り組んでいます。
全国的に少子高齢化が進んで人口が減少していく中で、人口増加率が全国2位の滋賀県においては当院の役割は大きく、整形外科のニーズも益々高まっていくと考えられます。
当科について

診療・指導体制の概要
当院は、京都府立医科大学付属病院整形外科を基幹病院とする日本専門医機構認定の「京都府立医科大学整形外科専門研修プログラム」の連携病院の一つであると同時に、独自の「済生会滋賀県病院整形外科専門研修プログラム」があり、整形外科専門医の育成を行っています。当院プログラムに専攻医として入職しますと、3年9カ月の研修期間のうち、1年9カ月は当院および滋賀県内の連携病院で、残りの期間は主に京都府医科大学と京都・大阪府内の連携施設で専門研修を行います。
研修コース(研修施設のローテーション例)
| |
1年目 |
2年目 |
3年目 |
4年目 |
| 例1 |
済生会滋賀県病院 |
京都第二赤十字病院 |
京都府立医科大学病院 |
| 例2 |
済生会滋賀県病院 |
京都府立医科大学病院 |
京都第一赤十字病院 |
| 例3 |
済生会滋賀県病院 |
京都府立医科大学病院 |
市立大津市民病院 |
亀岡市立病院 |
| 例4 |
京都府立医科大学病院 |
祐生会みどりヶ丘病院 |
済生会滋賀県病院 |
| 例5 |
京都府立医科大学病院 |
済生会滋賀県病院 |
がくさい病院 |
| 例6 |
関西医科大学病院 |
済生会滋賀県病院 |
亀岡市立病院 |
入院診療においては、専攻医は指導医とペア(担当医/主治医)となって、術前計画から手術、術後管理、リハビリテーション指導までを担当します。指導医とのペアは、各専門領域が満遍なく習得できるように、1ヵ月毎に組み換えます。
外来診療は、新患外来と再診診療を週に1回ずつ担当しますが、常に指導医に相談できる体制を整えています。
整形外科の救急診療体制は、日勤帯は若手常勤医と専攻医が救命救急センターの担当医として救急応需し、当直帯や休日は日直・当直医対応またはオンコール体制を敷いて整形外科の24時間対応に努めていますが、専攻医が日・当直の場合にはセカンドコールも決めて、万全のバッククアップ体制を整えています。専攻医の日・当直回数は、平日は月に2回、土日は月に1回程度ですが、当直明けは遅くとも午後から退勤することを厳守してもらっています。
週間スケジュールの一例
| |
8時35分~ |
AM |
PM |
17時~ |
| 月 |
ショートミーティング |
外来診療 |
手術・病棟回診・救急応需 |
|
| 火 |
ショートミーティング |
手術・病棟回診・救急応需 |
|
術前症例検討会 |
| 水 |
ショートミーティング |
|
|
|
| 木 |
ショートミーティング |
|
|
術前症例検討会 |
| 金 |
ショートミーティング |
外来診療 |
|
|
学習・研鑽については、指導医が各々の専門分野について専攻医向けにレクチャーを行います。学会・研修会の発表は年1回をノルマとし、論文作成までを指導医が責任をもって指導します。
年次休暇は1年の勤務期間につき20日付与され、夏季休暇の取得も義務としていますので、濃密な整形外科診療(研修)のあと十分にリフレッシュすることが可能です。